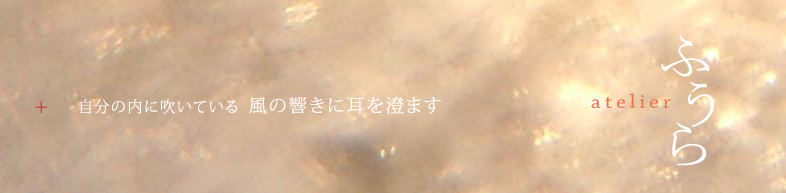しみむらさきさん
しみむらさきさん

むかーし昔、あるところに
一人のおばあさんがおりました。
おばあさんは、毎日
川へ洗濯に出かけてゆきました。
おばあさんは、しみのたくさんついた
紫色の着物を持って、毎日川へゆくのでした。
その着物はおばあさんのおばあさんが
おばあさんのお母さんのために
こしらえた着物でした。
おばあさんのおばあさんのお母さんは
おばあさんのおばあさんがお嫁に行く時に
綿を紡ぎ、山の木の実で糸を染め
機を織り、きれいな紫色の着物に仕立てて
おばあさんのおばあさんに持たせたのでした。
おばあさんのおばあさんは
その着物を、それはそれは大事にして
「大切な時にこの着物を着ましょう」と
すぐには袖を通さずに
箪笥の奥にしまっておりました。
幾月かが経ち
おばあさんのおばあさんのおなかに
赤ん坊ができました。
いよいよ生まれるという日の朝
おばあさんのおばあさんは
しまっておいた紫の着物を身につけました。
おばあさんのおばあさんのだんなさんは驚いて
「赤ん坊を産む時に、そんな大事な着物を着たら
汚れるじゃないか。」と言いました。
おばあさんのおばあさんは、にっこり笑って
「今日は私の一番大切な日だもの。
この着物を着るわ。」と答えました。
そうして元気な女の子が生まれました。
おばあさんのお母さんです。
赤ん坊は
ふわふわと柔らかくて白いおくるみに
くるまれているのが好きでした。
ゆらゆらと揺れるお母さんの腕の中で
目を閉じたまま、いい匂いに包まれながら
子守歌を聴いているのが大好きでした。
だんだんと目が見えるようになってくると
ふわふわの白の向こうに
美しい紫色が見えました。
赤ん坊はその美しい色合いを
眺めるのが好きでした。
紫色の着物でないと赤ん坊がむずがるので
おばあさんのおばあさんは
毎日その紫色の着物を着るようになりました。
「赤ん坊が今日もこうして無事に
生きてくれているのだもの。
毎日がお祝いの日だわ。」
おばあさんのおばあさんはそう言って
毎日大切な紫の着物を着て
赤ん坊をおぶって仕事をするようになりました。
紫色の着物は、あっという間に
赤ん坊のよだれや鼻水や、涙や料理の汁や
雨の日の泥水などで、たくさんしみができました。
村の中で普段着に
紫色の着物を着ているだけで目立つのに
それがしみだらけなので
もうそれはそれは目立ちます。
おばあさんのおばあさんは、いつしか村の人達から
「しみむらさきさん」と呼ばれるようになりました。
おばあさんのおばあさんは
そんなことにはおかまいなしに
しみだらけの紫色の着物を着て
赤ん坊を抱きながら
しあわせな気持ちで暮らしていました。
赤ん坊だったおばあさんのお母さんは
すくすくと育ってゆきました。
だんだんと、大きくなるにつれ
白いおくるみの気持ち良い肌触りや
ゆらゆらと揺れる感覚や
お母さんのいい匂いや
子守歌の心地よさなんかを
すこうしずつすこうしずつ
知らない間に、忘れていきました。
おばあさんのおばあさんも
赤ん坊のおねだりが無くなってきたので
だんだんと普通の絣の着物を
着るようになっていきました。
少女になったおばあさんのお母さんは
ある日仲良しの友達から
自分のお母さんが村の人達から
「しみむらさきさん」
と呼ばれている、ということを聞きました。
自分のお母さんが
「しみ」付きで呼ばれているなんて
あまり気持ちの良いものではありません。
「うちのお母さんはまだ若くてきれいで
しみなんて一つもないのに‥」
おばあさんのお母さんは
さっそく家に帰って聞きました。
「お母さんは、どうして
『しみむらさきさん』って呼ばれているの?」
おばあさんのおばあさんは
にっこり笑って、箪笥の奥にしまってあった
しみのいっぱい付いた紫色の着物をとり出して
おばあさんのお母さんに見せてくれました。
その着物があまりにもしみだらけだったので
おばあさんのお母さんはびっくりしましたが
おばあさんのおばあさんが何も言わずに
懐かしそうにしあわせそうに
そっと
そのしみだらけの紫色の着物を
なでているのを見て
「しみむらさき」という言葉が
不思議ときれいな音の響きに
思えてくるようになりました。
それからは、自分のお母さんが
「しみむらさきさん」と呼ばれていても
あまり気にならなくなりました。
おばあさんのお母さんも
いつの間にか、きれいな娘さんになり
お嫁にいく時がきました。
おばあさんのおばあさんは
この日のために、前の畑で綿を育て、糸を紡ぎ
山の木の実できれいな紫色の糸を染め
トントンパッタン、トントンパッタンと
機を織り、丈夫な着物を縫って
おばあさんのお母さんに持たせてあげました。
その着物があまりにも綺麗だったので
おばあさんのお母さんは、もったいなくて
お嫁にいった先でも
普段なかなか着ることができませんでした。
「これは、いつか特別な日に着ることにしましょう」
と箪笥の中に大事にしまっておきました。
幾月かが過ぎて
おばあさんのお母さんのおなかに
赤ん坊ができました。
今日生まれるなと感じた日の朝
ふいにおばあさんのお母さんは
あの紫の着物を着ようと思いついたのでした。
紫の着物に袖を通しているおばあさんのお母さんを見て
おばあさんのお母さんのだんなさんは
「なんだ、そんな特別な着物を着たりして」と言いました。
おばあさんのお母さんは、しあわせそうに笑って
「今日生まれそうな気がするの。だからこれを着るの」
と答えました。
紫色の着物をふわり羽織って床に横になると
着物から、懐かしいお母さんの匂いがしてきました。
ずっと長い間忘れていた匂いでした。
障子から差し込むやわらかい光の中で
懐かしいいい匂いに包まれて
まぶたを閉じてうとうとしていると
どこからともなくゆったりとした
優しい歌声が聴こえてきました。
「あれ?子守歌?」と思った瞬間
おばあさんのお母さんは
おばあさんのお母さんのお母さんが
いつもいつも紫の着物を着て
自分を揺らしてくれていたことを
思い出したのでした。
どうして、あの紫色の着物が
あんなにもしみだらけだったのかを
おばあさんのお母さんは
やっと理解しました。
懐かしさとありがたさの中で
涙がつうーっと頬を流れてゆきました。
子守歌は今
自分とおなかの赤ん坊の両方に
聴こえているのが感じられます。
眠っているような覚めているような
やわらかな光の中で
おばあさんのお母さんの息と
おなかの赤ん坊の息が
やわらかく一緒になって
まるでしずかな海の
おだやかな波のようでした。
ゆったりと安心した呼吸の中で
しずかにゆるりと
柔らかな女の子が生まれました。
それが
おばあさんです。
おばあさんのお父さんは
おばあさんが小さい頃に
早くに亡くなってしまいました。
おばあさんのお母さんは
明るくて働き者で
村の人達から大変好かれておりました。
が、なぜか皆から
「しみむらさきさん」という愛称で呼ばれていました。
「むらさき」はいいとしても
まだ若くてきれいで働き者のお母さんが
どうして「しみ」なんてついて呼ばれているのか
おばあさんは子どもの頃から不思議でした。
でも、おばあさんのお母さんが
あまり気にしている風でもないので
子どものおばあさんも
特に何とも感じていませんでした。
ある日おばあさんは
豆の殻むきを手伝いながら
ふと聞いてみたくなりました。
「ねぇ、母さんはどうしてみんなから
『しみむらさきさん』て呼ばれているの?
しみなんて一つもないのにさ」
おばあさんのお母さんは
「ふふふ、さあどうしてかしらねー」と
嬉しそうに笑って、豆をむきながら
おかっぱ頭のおばあさんのことを
幸せそうにただ見つめるだけで
これといって理由らしいことは
特に何も答えてはくれませんでした。
おばあさんがおさげ頭の娘さんになった頃
おばあさんのお母さんは風邪をこじらせて
そのまま亡くなってしまいました。
娘のおばあさんは
突然ひとりぼっちになりました。
村に親戚は何軒もあったのですが
おばあさんは、そのまま住み慣れた家で
一人で暮らすことにしました。
おばあさんのお母さんが亡くなった後
しばらくして、おばあさんは
お母さんの箪笥の整理をすることにしました。
娘になったおばあさんと
亡くなったおばあさんのお母さんは
背格好がほとんど同じだったので
どの着物も袖がぴったりでした。
「これからは、母さんの着物を着て暮らそうかな」
と、おさげ頭のおばあさんは
からりと明るく淋しい響きで
ぽつりひとりごとを言いました。
一枚一枚
着れそうな着物を選び出している時
箪笥の奥から
綺麗な透かし模様の和紙に丁寧に包まれた
着古した、しみだらけの紫色の着物を見つけました。
その着物があまりにもしみだらけだったので
おさげ頭のおばあさんはびっくりしましたが
「しみむらさきさんって呼ばれていたのは
この着物と関係があったのかなぁ」
と思った途端
「ふふふ、さあどうしてかしらね〜」と
しあわせそうに笑っていたお母さんを思い出して
急に涙がいっぱい溢れてきました。
綺麗な昔の和紙に丁寧に包まれた
しみだらけの紫の着物は
大好きなお母さんの形見として
宝物として
大切にとっておくことにしました。
おばあさんは、お嫁にいく時
お母さんの古い箪笥と
その中の着物達も道具として持っていきました。
おばあさんは男の子を3人産みました。
毎日の暮らしの中で、だんだんと
箪笥の奥のしみ紫の着物のことを
思い出す事もなくなっていきました。
子どもたちはみんなすくすく育ち
大人になり、結婚して
それぞれ遠くの街に出てゆきました。
おばあさんのだんなさんは
おじいさんになるまで生きて
おばあさんと仲良く暮らしていましたが
そのおじいさんも
とうとう二年程前に亡くなりました。
おばあさんは
毎日ぽかぽかと陽の当たる縁側で
ちょこんとおざぶに座って
大好きな黒豆のお茶を飲みながら
おじいさんがまだ生きていた頃のことや
子どもたちが小さかった時のことなど
むかし昔の日々の暮らしの
小さなしあわせなことごとを
ひとつひとつ思い出しては
毎日をのんびりと懐かしく
しあわせな気分で満たしながら
過ごしておりました。
ある暖かな春の日のこと
おばあさんはまた今日も
いいお天気の縁側で
息子達がこの間
誕生日のお祝いにと贈ってくれた
白いふわふわの綿の毛布にくるまって
しあわせな時間をうらうらしておりました。
あんまりお天気が気持ちいいので
目をつぶってまぶたの上で
ゆらゆらする暖かい光を楽しんでおりました。
すると
ふいに懐かしい感覚に包まれたのです。
「何だろうこれは‥
はっきりと思い出せないけれど
とても懐かしい感覚‥
私はこれが大好きだったような‥ええっと‥」
おばあさんがはっきりと思い出せないまま
懐かしい感覚にただただ身をゆだねていると
お日さまのぽかぽかした匂いにとてもよく似た
いい匂いがしてきました。
その匂いに包まれて
しずかに呼吸していると
とても安らいだ
しあわせな気分になれるのです。
と今度は、どこか遠くの方から
やわらかな波のような音が
かすかにかすかに聴こえてきました。
そのゆうらりとふうわりと揺れる波の中で
そっと耳を澄ますように
からだとこころを澄ましていると
やわらかな音の波間から
水のように澄んだ声の響きが
まるで子守歌のよう聴こえてきました。
その瞬間
「あぁ、しみむらさきの着物だ」
おばあさんは
はっきりと思い出しました。
おばあさんのお母さんが
いつもいつも紫色の着物を着て
自分を揺らしながら
子守歌をうたってくれていたことを。
子守歌を聴きながら
そのきれいな紫色を
白いおくるみ越しに眺めるのが
何よりも好きだったことを。
どうしてしみむらさきの着物が
あんなにもしみだらけになったのかを
おばあさんはこの時やっと理解しました。
おばあさんはすっくと立ち上がり
古い箪笥の引き出しを
次々と開けてゆきました。
一番下の引き出しの奥に
もうすっかり古くはなったけれど
きれいな透かし模様の和紙に包まれて
懐かしい、しみむらさきの着物はありました。
おばあさんはその着物を抱えて
近くの川へゆきました。
しみを洗おうと思ったのです。
いえ正確にはおばあさんは
「しみを洗い落としたい」
と思っているわけではありませんでした。
実はおばあさんにも
自分が一体何をしたいのか
よくわからなかったのです。
ただその着物を見た途端、無性に
川の水にくぐらせたくなったのです。
それで自分でもよくわからないので
川で着物を洗うふりというか
そんな感じで、ジャブジャブさせて
絞って、家に持って帰ってきたのでした。
濡れたものは、干さないといけないので
縁側から見える庭の物干し竿に干してみました。
その日はとてもいいお天気で
洗濯物のしみむらさきは
なんだかとても気持ち良さそうです。
おばあさんはそこまでしてしまうと
なにかほっとし
よっこらしょっと縁側にのぼり
またいつものお座布団の上に
ちょこんと座りました。
チチチチチ
と小鳥が鳴いています。
しずかです。
空が青いです。
青といっても夏の真っ青さや
秋の抜けるような遠い青さではなくて
どこかふわっとした
いかにも春という感じの
淡くて柔らかい青さ。
そのふわりとした青さの前で
しみむらさきが心地良さそうに風にゆれている。
そんな風に
しあわせそうにしているしみむらさきを見て
おばあさんは
からだ中から嬉しい気持ちが湧いてきました。
ぽかぽかした陽気の中で
単衣の綿のしみむらさきは
夕方にはもうすっかり乾いていて
おばあさんは赤子を抱くように
しみむらさきをそっと竿からはずし
部屋の中に連れて入りました。
次の日も、また次の日も
朝になるとおばあさんはいそいそと
しみむらさきを連れて川へ行き
ひとしきり水の中で遊ばせると
また家に連れて帰り
庭に干しては、日がな一日縁側で
しあわせそうに揺れているしみむらさきを
目を細めて眺め暮らすのでした。
来る日も来る日も、川へ行っては
同じしみだらけの着物を洗うおばあさんを見て
村の人達は
「あのおばあさんも、とうとうぼけちゃったのかねぇ」
と噂し
いつしかおばあさんは村の人達から
「しみむらさきさん」と呼ばれるようになりました。
となりの幼なじみのおばあさんが
毎日、三時のお茶の時間にやってきては
おばあさんが村の人達に
ボケたなんて噂されていることだとか
「しみむらさきさん」などと
呼ばれていることなどを
せっせと知らせてくれるのですが
おばあさんは、何を聞いても
「へぇ、そうかい、ほぅ、そうかい」と
聞いてるのか聞いてないのか
わからないような返事をしては
ただただニコニコしているので
となりのおばあさんもだんだんと
うわさ話のうわさ話をすることに飽きてしまって
おばあさんと一緒にただ縁側に座って
今日もしみむらさきがゆらゆら空に
しあわせそうに揺れているのを見ているだけで
満足して帰ってゆくようになりました。
どんなに噂されようとも
おばあさんはそんなことにはおかまいなしに
ただただ、しみむらさきと一緒に
しあわせな毎日を過ごしておりました。
おばあさんはだんだんと
目が見えなくなってきましたが
見えにくくなるにつれ
素敵なことがはじまりました。
しみむらさきと再会したあの日から
しみむらさきを陽に干すとかならず
どこか遠くの方から
あのやわらかな波のような音が
かすかにかすかに
聴こえてくるのです。
その揺れる波の中で
しずかにそっと耳を澄ましていると
やがてやわらかな音の波間から
声の響きの子守歌が聴こえてきます。
最初の頃は
耳を澄ましてやっと聴き取れるぐらいの
かすかさだった子守歌が
だんだんと
目が見えにくくなるにつれ
はっきりと透き通った響きで
からだ中にやわらかく
響き渡るようになってきたのでした。
だんだんと目が見えなくなってきていたおばあさんも
もともと視力の弱い隣のおばあさんも
おばあさんの姿を遠くから眺めては噂している村の人達も
誰一人として
しみむらさきのしみが、洗う度に少しずつ
濃くなってきていることに
気づく者はおりませんでした。
縁側に座り、白いふわふわの
綿の毛布のおくるみにくるまって
まぶたを閉じると
お日様の明るいあたたかさを感じます。
からだのまわりは
大好きなあのいい匂いで包まれています。
子守歌の響きを聴きながら
うとうとするおばあさんの頭を
風がそっと、よしよししてゆきます。
今では
もうすっかり目が見えなくなってしまった
おばあさんですが
光とあたたかさと
やわらかさといい匂い
そしてきれいな響きに包まれて
ただしあわせでした。
眠っているのと目覚めているのの
間のようなしあわせの中で
ある日おばあさんは
しずかに息をひきとりました。
まるで
眠っている赤ん坊のような顔をして・・
三時のお茶に来た隣のおばあさんが
あわてて村の若い人達を呼びに行きました。
駆けつけた村の人達は
庭で風に揺れているしみむらさきを見て
あっと息を呑みました。
しみだらけだったはずのあの古い着物が
紫色の全身に、淡い色とりどりの
美しい花を咲かせていたのです。
それはそれはみごとな花の文様でありました。
亡くなったおばあさんは、いつしか
「はなむらさきさん」と呼ばれるようになり
その美しい紫の花の着物は、村の宝物として
いつまでも大切にお祀りされたということです。
おしまい
この「しみむらさきさん」の物語は
こんな風に子守歌を歌い聴かせながら語られる
眠りの物語として
親から子へ
子から孫へと代々語り継がれているそうな‥
(子守歌屋 POOL)
⇩
a:189 t:1 y:0